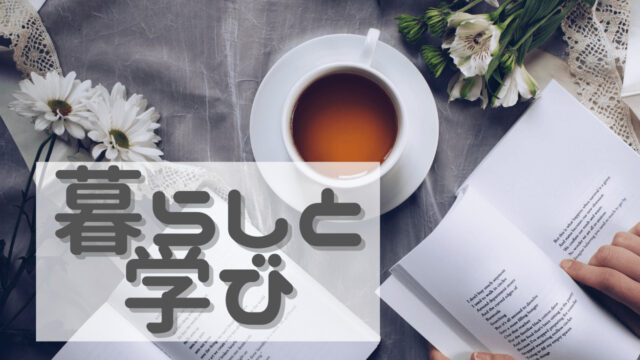こんにちは、いち(@ichigo_ichi_a)です。
ジュニアNISAは投資できる枠が1年間に1人80万円と大きいので、投資する金融商品を迷っている方も多いのではないでしょうか。
我が家ではこれまでも投資信託のeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をジュニアNISAで運用していましたが、先日残っていた枠(40万円×2)で米国ETFを購入しました。
- ジュニアNISAで外国株投資をしたいと考えている
- 米国ETFの購入方法が知りたい
【ジュニアNISA】SBI証券で米国ETFを購入する方法

令和2年度の税制改正により2023年で終了・廃止が決定したジュニアNISA。
しかし、それによって払い出し制限が撤廃されたことで使いやすくなったとして開設する人が増えてきています。
ジュニアNISAを使って投資信託を購入している方が多いと思いますが、NISA枠では分配金も非課税なので米国個別株やETFを購入するのも1つの選択肢かなと思います。
我が家ではSBI証券で実際に子どもの米国ETF(VIG、VYM)を購入したため、その方法を詳しくまとめました。
以下の順で説明します。
- SBI証券で買付できる金融商品
- 実際の買い付け方法
- 現在の状況
SBI証券で買付できる金融商品
- 国内株式(REITやIPOも対象)
- 投資信託(株式型、債券型、バランス型、コモディティ型)
- 外国株式(アメリカ、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF)
ジュニアNISA口座を開設できる証券会社はたくさんありますが、外国株式取引ができるのはSBI証券のみです。
投資信託の取り扱い本数も2580本と(2020年資料参照)楽天証券と並んでトップクラス。すべて手数料0円なのも安心です。
実際の買い付け方法
- ログイン後、外貨建商品取引サイトへ
- 買付したい銘柄を選択
- 口数や預かり区分を入力し注文確認
買付は入金済みで、商品が決まっていればすぐにできます。
①ログイン後、外貨建商品取引サイトへ
SBI証券へログインしたら、外国株式の取引ボタンをクリックします。

外貨建商品取引サイト(下画像参照)が別ウインドウで開きます。
②買付したい銘柄を選択
次に、買付したい銘柄かティッカーを入力し検索。

今回購入したものの1つはVIGというティッカーのETFです。銘柄名はバンガード米国増配株式ETFとなります。
VIG(バンガード米国増配株式ETF):ナスダック米国ディビデンド・アチーバーズ・セレクト指数に連動する投資成果を目的とする。米国の中型・大型株を保有。過去10年間連続増配の米国の普通株(REITを除く)への投資に注力する。
2021年上記組入れ銘柄:マイクロソフト、ウォルマート、ディズニー、ジョンソンアンドジョンソンなど
BloombergHPより引用
検索結果のところで取引したい商品の買付ボタンをクリックします。

③口数や預かり区分を入力し注文確認
注文入力画面にうつるので買付したい口数を入力。(今回は12口、約20万円分買付しました)
指値もできますが長期で保有する予定であれば、成行でも良いかと思います。
指値:買う値段を指定して注文する方法(指値以下の株価にならなければ注文は成立しない)
成行:その場で注文が成立する方法
預かり区分は必ずジュニアNISA口座ーNISA預かりを選択してください。

15歳未満で住信SBIネット銀行に口座を開設することができない場合には、外貨を買付することができないため円貨決済を選ぶことになります。
最後に取引パスワードを入力して注文確認画面へのボタンをクリックします。これで取引完了となります。
現在の状況

現在の評価額は口座管理の保有証券・資産のページを選択すると見ることができます。

まとめ
- 外国株取引はSBI証券のみ可能
- 配当金のしくみも子どもに伝えられる
- 以下のとおり、外国株は簡単に買付できる
- ログイン後、外貨建商品取引サイトへ
- 買付したい銘柄を選択
- 買付したい口数を入力
- ジュニアNISA口座ーNISA預かり、円貨決済を選び、注文確認
ジュニアNISAは1年間に1人80万円までの枠で運用でき、制度が終了する2023年までに投資した分の運用益や分配金は全て非課税となります。
投資信託だけの方がトータルリターンは大きいと言われていますが、米国ETFも合わせて購入することで、子どもたちに配当金という仕組みも伝えていくことができると思い、我が家はETF買付を決めました。
子どもの教育資金をすべて投資で運用するのはリスクが高いですが、合わせて貯金も行いながらバランスをとっていくことが大切です。
今回の記事が少しでもみなさんのお役に立てば嬉しいです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
投資は元本保証ではないのであくまで自己責任での選択をお願いいたします。